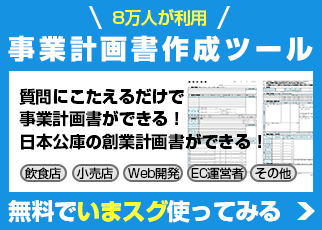新規事業を立ち上げ、会社が軌道に乗り始めたころ、経営者が考えるのは「人を雇って事業を拡大させたい」ということでしょう。
人を雇用するということは、企業と労働者の間に「雇用契約」を締結するということです。そしてこの雇用契約は「労働基準法」「労働契約法」といった労働法によって多岐にわたる規制がなされています。
このコラムでは、複数回に分けて、ベンチャー企業が人を雇う際に気をつけるべき点(これを「労務」といいます)をピックアップし、解説していきます。
- 目次 -
残業代とベンチャー経営のリスク
「残業代」の定義とは
「労働基準法」では、会社が1日8時間、週40時間を超えて従業員を働かせることはできないと決められています。これを法定労働時間といいます。
会社と従業員との間で「三六協定」(労働基準法36条に基づく使用者と労働組合等の協定)が締結され労働基準監督署に届け出されている場合は、この時間を超えて働くことができますが、その場合でも「①1日8時間を超えて働いた時間」や「②週40時間を超えて働いた時間」はすべて残業時間(時間外労働)になります。
時間外労働=残業には、基本給に比べて25%以上割増した賃金を支払わなければならないと定められています。この、時間外労働に対して支払われる賃金を「残業代」と呼んでいます。
残業代の消滅時効は2年間
使用者(経営者)は、毎月毎月この「残業代(時間外労働に対する割増賃金)」を計算して基本給の他に各労働者に支払う義務があります。支払わない場合、毎月毎月の未払い残業代を一括して請求されるリスクがあります。残業代の消滅時効は2年間ですので、長期にわたり残業代を支払わないと、最長24ヶ月分の残業代を一括して支払うことになります。
一度に予定外の支出を迫られることになるので、ベンチャー企業の資金繰りに多大なる悪影響を及ぼしかねません(従業員が「私も私も」と手を挙げると、その数倍の金額に膨れ上がります。)。
労務整備はベンチャー企業のリスクヘッジ
このようなことがあるので、人を雇う際には、残業代のルールを正しく理解し、法的に正しい制度を整備して、必要な賃金の額を計算しておく必要があります。
このような作業は一見面倒ですが、後日未払い残業代請求の裁判で争うこと(紛争法務)に比較すると、はるかに低コストで確実性があります。このような予防法務の観点から、経営に法務を取り入れることを心がけていただきたいと思います。
本当に「残業代は払わなくて良い」のか
ベンチャーに限らず、巷の企業では「うちは○○だから残業代は払わないよ」などという話が当然のようになされています。そして、従業員も「そうなのか」と妙に納得している例もあります。果たして本当に支払わなくても良いのでしょうか。それが勘違いであった場合、使用者(経営者)は残業代未払状態ということになりますので、リスクをはらんでいることになります。
「年俸制だから残業代は払わないよ」
このような話は、よくお聞きになるのではないでしょうか。結論をいいますと、そのようなことはありません。年俸制であろうが労働時間に関する規制は同様であり、一日8時間、週40時間を超えて従業員が働いた場合には、残業代を支払わなければなりません。
「固定残業代(みなし残業代)を支払っているから残業代は支払わないよ」
これも主にベンチャー企業でよく聞く話です。そもそも固定残業代(みなし残業代)とは何でしょうか。
「固定残業代」とは一定額を事前に支払うだけのもの
固定残業代とは、毎月の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払う制度をいいます。残業代は事前の見込みに合わせて定額で支給する制度と考えると良いでしょう。そして、この制度はあくまで見込み額を支給するものですので、実際の残業時間に応じて計算した残業代が固定残業代の額を超えた場合は、企業はその超過額を支払う必要があります。
支払わなくてよくなる制度ではなく、一定額を事前に支払うだけですので、足りない分については事後に精算する必要があるのです。
「固定残業代」じたいの有効性を問う裁判ケースも多い
また、固定残業代の定め自体の有効性が裁判で争われるケースも多くあります。例えば月給30万円を支給している企業について、25万円は基本給、5万円が固定残業代であると主張したとしましょう。
もし事前に5万円という金額と、それに対応する月間の時間外労働時間を定めていない場合、有効な固定残業代の定めであると認定されない可能性が高いといえます。きちんと時間と金額については定める必要があります。
最高裁判所の判例(最判昭和63年7月14日労判523号6頁)においても「基本給の中に割増賃金を組み込んで支給する場合については、労基法所定の割増賃金が支払われているかどうかを判定するために、割増賃金に相当する部分とそれ以外の部分が明確に区別されていなければならない」とされています。
固定残業時間の目安は「45時間」
固定残業代の時間をあまりに長時間を設定するというのも、有効性を否定されかねません。
東京高裁の裁判例(東京高判平成26年11月26日労判1110号46頁・マーケティングインフォメーションコミュニティ事件)は、100時間分の固定残業代を定めた企業について
としており、基本的には45時間を一つのラインとして有効性を判断しているといえるでしょう。
別の手当を固定残業代とすることもリスクがある
さらに、別の手当を固定残業代としてみなすケースも散見されますが、これも裁判例では否定されるケースが多くあります。
例えば東京地裁の裁判例(東京地判平成24年6月29日労働判例ジャーナル7号10頁)は賃金規程に「営業手当は、就業規則15条による時間外労働割増賃金で月30時間相当分として支給する」との定めがあるケースです。
これについて裁判所は
としています。
ただ単に定めがあるというだけではダメで、対価性と計算方法(時間と額が連動するようになっているか)を裁判所が厳格に審査することになります。ただ単に、他の手当を残業代として振り替える定めをおいても、有効ではありません。
「裁量労働時間制だから残業代は支払わないよ」
「裁量労働時間制」とは、実際働いた時間に関係なく、事前に決めた時間(これを「みなし労働時間」といいます)働いたと「みなす」勤務体系です。
例えば、みなし労働時間を1日8時間とした場合には、労働時間が5時間でも、10時間でも、8時間労働したこととして扱われます。
みなし労働時間が法定労働時間内であれば、論理的には時間外労働(法定労働時間を超える労働)自体が発生しませんので、確かに残業代は発生しないと言えます。
しかし、そもそも裁量労働時間制は悪用されやすい制度ですので、いくつもの要件をクリアしなければなりません。対象業務自体限定されている上、労使協定を結ぶ必要があります。この手続をきちんとやっていない企業も、少なからず存在してしまっています。
また①みなし労働時間自体が8時間を超えている場合には当然残業代は発生します。さらに②深夜、休日に関する割増の適用はあるので、実際の労働が深夜や法定休日である場合には、その分割増をして支払う必要があります。
ベンチャーにおける「残業代」対策としての予防法務、労務の内容
では、従業員に一日8時間、週40時間を超えて労働してもらいたい場合、使用者(経営者)としてはどのような準備をする必要があるでしょうか。
まず、就業規則における記載等により、所定労働時間を超える労働を労働契約上義務付ける必要があります。また、法定労働時間を超える労働をさせる場合には、三六協定を労使間で締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ていることが必要です。三六協定は届出を行わないと発効しないため注意してください。さらに、法定で定める率以上の割増率で計算した割増賃金を支払うことも必要です。
そして、自社がとる給与体系について、整備し直す必要があります。固定残業代を支給する場合には、適切なみなし時間、金額を設定し、きちんと残業代であることを明示しておく必要があり、超過分については速やかに支払うことになります。
裁量労働時間制を取る場合には、そもそも労基法上許されているのか、休日深夜の労働状況について把握しているのか、検討する必要があります。
さいごに:ベンチャー労務の課題
ベンチャー企業にとって「人を雇う」ということは事業拡大の大きな一歩であり、かつ法的トラブルの最初の大きな落とし穴であるともいえます。悪意があってもなくても、労働法に反する雇用をしてしまうと、信用を失うばかりか金銭的にも莫大なしっぺ返しを喰らいます。
「人を雇う」前に、十分に法律の専門家に「予防法務」の観点からアドバイスを受け、万全の体制で労務を開始するべきです。ベンチャー企業に限らず、残業代は近年非常にポピュラーな労務紛争ですので、本コラムをお読みになって自社の労務をチェックしたいと思った経営者は、早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 秋元 啓佑氏
(三和法律特許事務所 弁護士)
中小企業やスタートアップ企業の基礎的な法律問題から、複雑な知財、労働案件など数多くの法律に関するお悩みの解決を行う。
chatwork/LINE@/skypeを用いたオンラインによる法律顧問業務を提供し、スマホ一つで法律の悩みを解決するサービスが好評。

この著者の記事を見る
- 2019年6月5日 【弁護士が解説】法的観点から
バイトテロを防ぐには? - 2019年4月3日 損害賠償判決から学び、ハラスメントを防ぐ
- 2018年11月21日 【弁護士が解説】
ネット上でよく見かける契約書テンプレートは使って大丈夫? - 2018年11月7日 プロダクトデザインの著作権
~TRIPP TRAPP事件~ - 2018年11月1日 民法(債権法)改正によって時効が変わる?