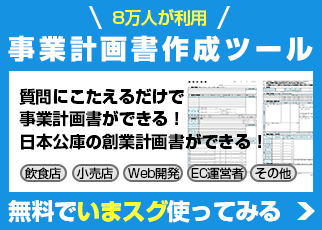- 目次 -
第59回
ぴあ株式会社 代表取締役会長兼社長
矢内 廣 Hiroshi Yanai
1950年、福島県生まれ。中央大学法学部在学中、このままレールに敷かれた会社員の道に進むのは癪だと、大学3年からバイト仲間たちと『ぴあ』の創刊準 備を開始。さまざまなハードルをクリアし、1972年、『ぴあ』を創刊。1974年、ぴあ株式会社を設立し、代表取締役に就任した。1977年、映画監督の発 掘・育成を目的とした「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」の前身「第1回自主製作映画展」を開催。1984年、「チケットぴあ」スタート。1998 年、長野オリンピックのオフィシャルサプライヤーとしてチケット販売を担当し、冬季五輪史上最高の入場券販売率を記録(当時)。2002年、東証二部に上 場。2003年、東証一部に指定替え。2007年7月に、創業35周年を迎えた。
ライフスタイル
好きな食べ物
カレーライスです。
昔は、夕食にカレーライスを食べて、翌朝もカレー、学校に持っていく弁当もカレー。それくらいカレーが続いてもまったく飽きませんでした。今はそれほどで はないですが、相変わらずカレー好きです。お酒はいけるほうだと思います。毎晩のように会食が入っていますから、平日はほぼ毎晩たしなみます。
趣味
俳句です。
10年くらい前に友人に誘われて始めたんです。最初は先生について教えてもらいました。紙と鉛筆があればできる趣味ですし、普段から季節感を考えながら生 活するようになりましたね。仕事で使う言葉と、俳句で使う言葉はまったく違います。日本語の豊かさを改めて知ることができたことも、俳句のおかげなんです よ。
行ってみたい場所
宇宙とか。
アーサー・C・クラーク原作で、スタンリー・キューブリックが監督をしたSF映画『2001年宇宙の旅』を初めて観た時の衝撃はすごかった。自分が見たことのない真実をこの目で確かめたいという意味で、いつか宇宙に行ってみたいとは思いますね。
最近、感動したこと。
東山魁夷展。
東京国立近代美術館で開催されている「生誕100年 東山魁夷展」を観に行きました。以前、唐招提寺で観た東山魁夷さんの襖絵に感動したのです。それが東京で観られるとあって、すぐに出かけたんですよ。展示 の仕方が唐招提寺と違っていたのは残念でしたが、東山さん本人の語りによる解説が聞ける音声ガイドは必聴です。
自分の不満を解消でき、周囲も喜んでくれること。
東京での生活経験が『ぴあ』着想の原点です
今では誰でも当たり前と思えることでも、それを最初に世の中に広めるために行動した人物が必ずいる。もちろん何かを発信したいと思っても、「そんなものはうまくいくはずがない」と人に言われ、あきらめてしまう人も多い。1972年に産声を上げた情報誌『Weeklyぴあ』(当時は月刊ぴあ)、1984年に運営を開始したチケット販売システム「チケットぴあ」は、私たちがレジャー・エンタテインメント情報を手に入れるための煩雑さと時間をいっきに軽減してくれた。これらの新しい仕組みを考案し、かたちとして世の中に送り出したのが、ぴあ株式会社の矢内廣社長である。1972年の創刊当時、矢内氏はまだ22歳の大学生だった。もちろんその頃に、学生ベンチャーなどという言葉は存在していない。「自分自身が便利になるものだから、もっとたくさんの人に使ってほしいと思ったんです。もちろん軌道に乗せるまでは試行錯誤の連続でしたが、多くの方々の協力があったからこそ『ぴあ』は日の目を見ることができたのです」と語る矢内氏。今回は、学生ベンチャーのパイオニア的存在である矢内氏に、青春時代からこれまでに至る経緯、大切にしている考え方、そしてプライベートまで大いに語っていただいた。
<矢内 廣をつくったルーツ1>
初めてのビジネス体験は、 小学校時代の甘納豆販売
生まれは福島県のいわき市で、家族構成は両親と3つ下の弟がひとり。父は普通の会社員です。自分でもなぜだかわからないのですが、昔から人に喜んでもらうことが大好きでした。あれは小学3年生の頃だったと思います。駄菓子屋でくじ付きの甘納豆を売っていたんですよ。1回5円だったかな。小さな袋に甘納豆が少しだけ入っていて、台紙に張られた甘納豆の袋を取り外すと当たりはずれがわかるんです。1等が出るとけっこういいおもちゃがもらえるという。私はそれが面白くて、駄菓子屋に行くたびにいつもそのくじ付き甘納豆を買っていました。
母はそんな私を見て勘違いしたんでしょうね。「ああ、この子はそんなに甘納豆が好きだったのか」と。ある日、母が丼に一杯分ほどの甘納豆をつくってくれたんですよ。もちろん嫌いではないですが、自分ひとりでそんなに食べられないじゃないですか。そこでこの甘納豆を使ってみんなに喜んでもらえることはないだろうかと考えたわけです。当時はまだ紙芝居屋さんとかが普通にいましてね。私はマンガを描くことがちょっと得意でしたので、自作の紙芝居をつくってみんなに声をかけて、甘納豆を売ってみることにしたんです。1等が出たら甘納豆がたくさん入った袋がもらえるという。
これが大好評で、たくさん人が集まって、甘納豆もたくさん売れた。もちろんみんなとても喜んでくれました。それで小銭をポケットに詰め込んで、じゃらじゃらいわせながら得意げになって家に帰ったら、母のカミナリが落ちるのです。「そのお金はどうしたの?」「甘納豆をかくかくしかじかで売った」「子どもの分際でいったい何を考えているの!」と、思い切りなぐられた(苦笑)。「誰に売ったか思い出しなさい。これから全員の家にお金を返しに行くから」。母と一緒に、お詫び行脚ですよ。結局そんなミソはつきましたが、あれが最初のビジネス体験だったんですね。
<矢内 廣をつくったルーツ2>
18歳で東京に出てきた映画少年が、カウンターカルチャーに衝撃を受ける
大人になって地元の同窓会に参加した時のこと。友人から「矢内君は遊んでいる途中で、何度も勝手にルールを変えていたよなあ」と言われたんです。そ れで、「ああそうだった」と思い出しました。子どもの頃、うちには友人がたくさん遊びに来ていて、ゲームをやったり外に出て缶蹴りをやったり、いつも大勢で遊んでいました。何かに熱中して遊んでいても、いったん「こういうやり方にすれば絶対にもっと面白くなる」と思うと、すぐに中断して「みんな、これからはこうしてみよう!」とやってしまうわけです。もちろん自分が有利になるためのルール変更ではなく、純粋に遊びをもっと面白くしたいだけ。先ほどの甘納豆売りの話も、遊びのルール変更の話も、結局はみんなに喜んでもらいたいから。“ぴあ”を始めようと思った原点も、そこにあるんですよね。
福島にいる時からずっと映画が大好きで観ていました。当時は日活や東映のチャンバラ映画が最盛で、毎週上映作品が変わっていましたよ。田舎で一番の娯楽といえば映画。そんな時代でしたね。その後、東京の大学に進んで、自然な流れで映画研究会に入って、映画を観に行くたびに衝撃を受けるわけです。起承転結がしっかりした勧善懲悪ものの映画ばかり観てきたのですが、東京はヌーベルバーグなんですよ。ゴダールの『気狂いピエロ』を観た時なんか、「こんなのありなんだ!?今まで観てきた映画はいったいなんだったんだ?」ってぶっ飛んじゃいましたから。
特に新宿は面白い街でした。芝居であれば寺山修司さんの天井桟敷、唐十郎さんの紅テント、映画館ならさそり座、昭和館にATGのアート・シアターがあって、松竹ヌーベルバーグの映画監督として、大島渚さん、吉田喜重さん、篠田正浩さんなども出始めていて。60年代後半から70年代にかけて、東京にはアンダーグラウンドやカウンターカルチャーがどんどん流入し、新しい映画の小さな波がちょうど大きなうねりに変わっていくような。18歳で東京にやってきた若き日の私は、どんどん映画にのめり込んでいくんですよ。
<矢印の街に情報の羅針盤を!>
学生の発想が大人の社会につながるか。その挑戦に面白みを感じ就職を断念
当時は学生運動の末期で、大学もロックアウトされて授業もあまりなく、生活費を稼ぐためにいろいろなアルバイトをしました。何とか生活費は稼げても、新作封切りのロードショーは高いですから高嶺の花で、安く観ることができる名画座など二番館、三番館を探して通うわけです。でもその頃は、上映館や上映スケジュールを網羅した情報がなくて、見逃してしまうことも多かったんですね。確かに、ひとつひとつの映画館は次回以降の上映情報を掲載した小さなチラシをくれるんですよ。でも、それだけではやはりダメで、いつどこの映画館でどんな映画をやっているか、東京中の情報がひとまとめで見られるメディアがあったらどんなに便利だろうと思っていました。
そんな発想に至ったのは、やはり東京で生活を始めてからです。東京にやってきて、新宿駅に乗り入れる電車の多さに驚いたことを覚えています。山手線、中央線、丸の内線に、小田急線、京王線……。いったいどう乗り換えればいいのか、最初はかなり戸惑いました。また、街に出ても大きなビルばかりでどこに何があるのかわからない。でも、表示された矢印をたどっていくと必ず行きたい場所に辿り着くことができる。ああ、東京は「矢印の街」だと思ったんですね。逆に田舎では、方角でだいたい説明がつくんですよ。山があっちだからこっちに行けばいい、風がこう吹いているからあっちが海だ、とか。もしも私が東京に出てこなかったら、“ぴあ”の発想は生まれなかったでしょうね。
“ぴあ”を始めるメンバーは、私が大学3年生の頃TBSでアルバイトをしていた時の仲間たちなんですよ。テレビニュース部というセクションで、学生バイトが20人くらいいたんですかね。彼らと居酒屋で就職の話もするのですが、私はこのままみんなと同じように会社員になるのは癪だと思っていて、自分たちで社会とのつながりが持てる仕事をつくれないだろうかとよく議論していたんです。大学生って、何かに守られている安心感があるんですけど、何だかリアルではない存在なんですね。でも、ここから発想される仕組みがリアルの社会で通用するかもしれない。そのチャレンジに、なぜだか私は面白さを感じてしまったんです。
<創刊準備スタート>
自分の下宿に電話を引き事務所として開放。毎日徹夜で“サンプル誌”づくりに勤しむ
「矢印の街」東京で、自分たちが観たい映画や演劇、コンサートなど、さまざまなエンタテインメント情報に辿り着くことができる情報誌をつくってみよう。そして仲間たちと“ぴあ”立ち上げの準備を始めたのです。まず、私が住んでいた下宿に電話を引きました。その頃は、ひとり暮らしの学生が下宿に電話を持つなんてありえない話だったのですが、TBSのバイトは冬にボーナスが5万円も出たんです。それを使わせてもらって。第五美咲荘という名前のアパートだったのですが、その玄関の表札に「月刊ぴあ編集室」という札をつけたら、大家さんに「矢内さん、何やってるの?」と聞かれましてね。「雑誌をやるんで。ご迷惑はお掛けしませんから」と。とりあえず事務所らしきものができました。
毎日、7、8人の仲間が泊り込みで下宿にやってきて、創刊準備をスタートさせました。最初にやったのはサンプルづくりです。できあがったサンプルを大学やアルバイト先の友人・知人に配って意見をもらうために。稚拙ではありますが、いわゆるマーケティングですね。すると「ほしい」「これがあったら便利だと思う」「100円なら買いたい」などなど、概ね好評な意見ばかり。ちなみに100円というのは当時のセブンスター1箱の値段です。これはいけるんじゃないかという手応えを感じることができました。
どろどろになって創刊準備を続けていたある朝、玄関をドンドンとノックする音で目が覚めました。ドアを開くと、そこにはなんと父が立っていた。小汚いかっこうをした仲間たちが何人も雑魚寝し、テーブルに置かれたラーメン丼には、タバコの吸殻が山盛りになっている。ひとり暮らしをしていると思っていた父はそんな部屋を見て、「お前はいったい何をやってんだ」と。「ここでは何だから」と、父を近所の喫茶店まで連れて行き、事情を説明することに。「卒業したらどこに就職するんだ?」「いや、雑誌をつくろうと思っている」。何も知らなかった父は、とても驚いていました。
1効率性・合理性追求の反動で“遊び”の価値が高まる。
今世紀・心の時代は、感動のライフライン構築が急務
<ピンチは成功への足がかり>
創刊号1万部の印刷は進めども、書店販売のルートが見つからない……
父が福島の実家からわざわざ訪ねてきた理由を聞くと、「大学から海外研修の手紙が届いたから」と。それは大学からの手紙のように見せたある旅行会社からの卒業旅行営業DMでした。父は「大学時代、お前に何もしてやれなかった。だから、海外研修にでも行かせてやろうと思って」と言ってくれたのです。父の気持はありがたく、嬉しかったのですが、私の方はそれどころではありません。「今は雑誌の準備で忙しくて行けないけれど、せっかく用意してくれたお金は、雑誌のために使わせてもらえないだろうか?」。黙って私の顔を見ていた父は、しばらくして「わかった」と言って帰りました。金額は28万円くらいだったと思います。
このお金があったおかげで、創刊号を印刷することができたんです。信用のない学生でしたから、前金じゃないと仕事を受けてもらえません。そして雑誌を本屋に流通させるため、本の取次会社の扉を叩いたわけですが、完全に門前払いされましたね。でも、それはある程度予想してました。当時は学生がつくったガリ版刷りのミニコミ誌がブームで、詩集や評論集などが大学の近所の書店に並べてありました。だから、同じように街の書店に頼めば置いてくれるだろうとタカをくくっていたんです。ところが、書店からも「売れるかどうかわからない雑誌を置くスペースなどない」と断られるばかり……。
もうこの時点ですでに原稿を印刷所に入れを始めていましたから、かなり焦りました。そんな時、たまたま「日本読書新聞」で元紀伊国屋書店社長の田辺茂一さんのインタビュー記事を読んだんです。「小売のマージンをもっと上げないといけない。このままでは日本から出版文化がなくなってしまう」そんな内容でした。『ぴあ』は取次店を通せませんから、本屋さんに直接持っていくわけで、取次店のマージン分も上乗せして書店に差し上げることができる。田辺社長のおっしゃっていることと、私の思いはぴったりじゃないか。そしてすぐにその記事に書いてあった電話番号に電話をかけるのです。いくつかの偶然が重なり、田辺さんに直接お会いできることになりました。自分の思いをお話したのですが、「そういう難しい話は俺じゃダメだな」。ということで、その場で日本キリスト教書出版販売という会社の中村義治さん(後の教文館社長)に電話をかけていただき、紹介いただいたのです。
<89店の書店販売からスタート>
偶然が重なって生まれた『ぴあ』は、多くの人の協力による授かり物
同じ話を中村さんにしたのですが、「雑誌はプロがやっても簡単にうまくいくもんじゃない。傷口を広げないうちにやめたほうがいいな」と諭されました。その後、どうお話をしたか覚えていないのですが、最終的には「わかった。どこの本屋さんに置きたいかリストにして持ってきなさい」と言っていただけたのです。そしてみんなで電話帳などを使いましたか、100軒ちょっとの書店をリストアップしました。それを持って中村さんに会いに行くと、「明日また来なさい」と言われ、そのとおり翌日もお伺いしたんです。すると中村さんのデスクに封筒が山積みされている。「これを持っていきなさい」と。何と書店への紹介状が用意されていたのです。僕らは書店のリストをお渡ししただけですが、その紹介状には、○□書店○△社長という宛名と、中村さんの署名と実印が押されてありました。この時の感動を、私は一生忘れられません。
その紹介状を持って、みんなで手分けして書店回りをやり直したのです。結果、なんと89店が置いてくださった。田辺さんと中村さんには、いくら感謝しても足りません。もうお二人とも他界されてしまいました。多くの方々の協力があってやっと何とか船出にこぎつけたわけですが、1万部刷った『ぴあ』創刊号は8000部の返本。つまり2000部しか売れませんでした。でも、何の宣伝もせず、ひとつの書店で平均20部売れたということは今考えれば悪い数字ではない。出版業界には「3号雑誌」という言葉があります。2号目の実売部数が落ち込んでも、3号目に創刊号の部数を超えることができれば大丈夫という目安です。『ぴあ』の第3号は、無事に創刊号の部数を超え、それから取次会社との取引を開始するまで、一度も前号対比の部数が落ちることはありませんでした。
直販でしたから配送のための運転手のアルバイトも募集し、書店の開拓を継続しました。店舗数が増えると、正比例以上に部数が伸びました。そうなると、書店側も放っておけません。書店の担当者が取次会社に「ぴあを扱いたい」と連絡を入れるようになった。そして創刊から4年目に流通会社から連絡があり、販売をゆだねる決断をするのです。その時、直販流通書店数は約1600店にのぼり、実売も10万部を超えていました。そして直販流通から解放され少し余裕が生まれた翌年、新人映画監督の発掘と育成を目的とした「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」の前身である「第1回自主製作映画展」を開催。大学の映画研究会では、3年になると映画をつくることができたのですが、私は『ぴあ』の準備を始めたので、それができなかった。PFFを始めた背景には、その時にあきらめた自分の夢を、後進たちに託したいという思いもあったのかもしれません。
<偶然が重なって生まれた『ぴあ』は、多くの人の協力による授かり物>
21世紀は心の時代。感動のライフラインを構築し続ける
PFFを続けてきた結果、最近、大変嬉しいことが立て続けに起こりました。2008年ベルリン国際映画祭で、PFFのスカラシップ作品『パークアンドラブホテル』の熊坂出監督が、最優秀新人作品賞を受賞。そして先日、アジア最高の映画を決める「アジア・フィルム・アワード」で、「第1回エドワード・ヤン記念・アジア新人監督大賞」に、昨年のPFFアワードでグランプリを獲得した『剥き出しにっぽん』を監督した石井裕也さんが選ばれました。さらに、これまたPFFのスカラシップ作品である『14歳』を監督した廣末哲万さんが、平成19年度芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。そして2008年の日本アカデミー賞で、『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』の松岡錠司監督が最優秀監督賞を受賞。前年は、『フラガール』の李相日監督が受賞。これらの監督全員が、PFF出身なんですね。また、先日発売された『AERA MOVIEニッポンの映画監督』で紹介された現代日本映画を代表する映画監督84人中28人がPFF出身でした。30年続けてきてこれ以上ないご褒美をいただけたよ うな気分です。
20世紀は物の時代、21世紀は心の時代と言われています。物の時代のインフラは、電気、ガス、水道といった生命維持のために必要とされるものでした。今や21世紀の世の中は、合理化や効率化に傾き、生身の人間にとって息苦しさを感じることさえあります。しかし、振り子が振れた分だけ反対に振れるのと同じように、私たちはその反動で非合理なもの、非効率なものを求めて心理的にもバランスをとるようになるでしょう。それは非生産的なもの、つまり“遊び”であり“芸術”であり、レジャー・エンタテインメントの世界だと思うのです。
ですから21世紀の心の時代に必要とされるライフラインは、ひとりひとりの毎日の暮らしを生き生きと感動的にするといった、心の豊かさをサポートするインフラなのです。私たち“ぴあ”は、これを“感動のライフライン”と名づけました。私たちは、人々がレジャー・エンタテインメント領域を楽しむために必要となる情報やサービスを届ける“感動のライフライン”を構築することが使命だと考えています。
<これから起業を目指す人たちへのメッセージ>
“HOW TO”の収集に時間を割くよりも、明確な“WHAT”を見つけることが先決
いろんな意味で、新しいビジネスが手がけやすい世の中になっていますね。最近は起業を目指している人々と話す機会も多いですが、みなさん“HOW”ばかりを求めているような気がしています。「どうやったらビジネスを立ち上げられるのか?」「どうやったらリスクを小さくできるのか?」と。そこで、私はその人たちに「あなたはそのベンチャービジネスを何のために始めるのですか?」「目的はお金ですか?」と聞くと、「はい」。もちろん経済性を満たすことは重要ですが、「それだけですか?」と聞くと答につまる。
私は“HOW”の前に“WHAT”、何のためにそれをやろうとしているのかということをビジネスを自ら創り出そうとする人に考えてほしいと思っています。企業が社会的に存続できるのは、世の中に貢献しているからです。この仕事は本来何のためにやっているのかという社会的使命、つまり“WHAT”をもっと自覚することが必要なのではないでしょうか。
やりたいことがあるなら、まず動き始めればいい。そして踏み切る時は、中途半端ではダメです。もしも失敗したら戻ろうと思えるような軸足を残さないこと。例え失敗しても何とかなる、命までは取られない。自分はそんな思いでやってきました。自ら生き方を創っていくのだという自己認識さえしっかりできていれば良いのではないでしょうか。
<了>
取材・文:菊池徳行(アメイジングニッポン)
撮影:山口雅之
専門家が48時間以内に回答!