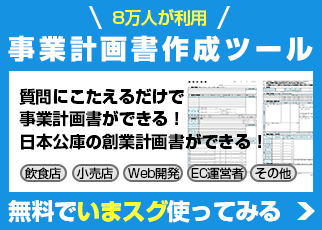- 目次 -
第33回
月刊ソトコト 編集長
小黒一三 Kazumi Oguro
1950年東京都生まれ。武蔵高校から慶應義塾大学法学部へ進学。卒業後はマガジンハウスに入社し、『月刊平凡』『ブルータス』『クロワッサン』『ガリ バー』などの雑誌編集に携わる。『ブルータス』編集部在籍中には中国、ブータン、ニューヨーク、ブラジル、アフリカなどを取材。1990年に退社後、ト ド・プレス設立。1992年、ケニアのマサイマラに、自らがプロデュースしたアフリカ人アーティスト、サイモン・ジョージ・ムパタの名前を冠したリゾート ホテル「ムパタ・サファリ・クラブ」をオープン。1995年、日本相撲協会創立70周年記念出版物『大相撲』を篠山紀信氏とともに制作。そのほか、テレビ 番組「ワーズワースの庭」「メトロポリタン・ジャーニー」、『中田語録』の編集、『スガシカオ1095』『築地』の出版など、さまざまな分野で数多くのプ ロジェクトに関与。1999年、環境ライフスタイルマガジン、月刊『ソトコト』創刊。「スローフード」「スローライフ」「ロハス」など、時代のキーワード とライフスタイルをいち早く提唱し続ける。
ライフスタイル
好きな食べ物
塩の入った沖縄豆腐
寿司とそば、あとは沖縄の豆腐だね。豆腐はワシタショップで、塩の入ってるやつを買う。この豆腐、2週間くらいもつんだよね。なんで東京でもつくらないんだろう。
趣味
『懐かしい未来』探しかな
これから面白い街ってどこだろうって、いつも探している。少し前は神楽坂なんか趣があったけれど、今はもう飽和状態でしょう。最近「懐かしい未来」って言 葉が気になっていて、自分の中でリストづくりを始めているんです。浅草、湯島、根津の店に行くんだけど、これって決定打がまだないんだよね。
酒
休みの日はひたすら飲み続けてる
お酒ほど時間と雰囲気と食べ物によって変わるものはない。だから何でも飲むよ。休みの日はひたすら酒飲む。まず朝風呂入ったあとにビール、続いて日本酒。 そして昼過ぎには酔っぱらって寝てしまう。だいたい3時間後に目が目が覚めて、近所のサウナに行って帰ってきたらまた飲む。そしてまた倒れて寝ちゃう。だ から休み明けの日はぐったりだよ(笑)。
行ってみたい場所
奥さんと子どものいない近所の家(笑)
きれいだなって思ったのは砂漠かな。でもサハラ砂漠にはもう行っちゃったしなぁ。そうだ、家の近所に奥さんと子どものいない家があったら時々行きたいかな。金がないからそんなの持てないんだけどさ(笑)。
楽しくオシャレに、快楽的なエコライフを実現。
『ソトコト』で提案しているのは、そんな世界観
環境ライフスタイルマガジン『ソトコト』が売れている。「スローフード」「スローライフ」「ロハス」といった、快楽的エコライフの楽しみ方をいち早く日本 マーケットで提唱してきたこの雑誌。ブレイクスルーとなったのは、環境博といわれた愛知万博だとか。以降、企業からの広告出稿は年々増加し、それに比例し て読者数も急増。一般読者は女性比率が高いらしいが、企業や官公庁のいわゆる仕事読者層が年々数を増やしているという。
環境保護への対応が、国や企業の存続を左右するといわれているこの時代。やっぱり人間、地味や質素な生活で耐え忍ぶより、できることなら楽しいエコライ フを送りたい。そうした提案が私たち日本人のニーズにぴったりはまり、『ソトコト』は21世紀のムーブメントフラッグシップメディアのポジションを獲得し たのである。
この雑誌を仕掛けたのが、マガジンハウス時代、『ブルータス』をはじめとする雑誌の名物編集者として数々の逸話を残してきた小黒一三氏。今回は、自身も快 楽生活主義者を自任する小黒一三氏に、青春時代からこれまでに至る経緯、大切にしている考え方、そしてプライベートまで、豪快にして軽妙洒脱に語っていた だいた。
<小黒一三をつくったルーツ.1>
幼少のころは神童扱い。勉強もスポーツも賢くこなす
生まれは東京。2歳で豊島区の椎名町に引っ越したんだけど、実家は築地のマグロ問屋です。3人兄弟の真ん中で、放任主義で育てられたせいか、まぁ子 どものころから相当に変わり者だったらしいよ。おふくろがよく言っていたけれど、周りの子どもたちが大きくなったら博士か大臣か、なんて将来の夢を語って いるときに、僕は汚穢屋になりたいなんて言ってたんだって(笑)。それに加えてかなりの暴れん坊で、兄弟喧嘩なんか日常茶飯事。手がつけられなかったらし い。それでひとりだけ四谷の親戚の家に2、3年間預けられてたんだ。
それでも勉強はよくできたんだ よね。親から勧められて塾にも通っていたし、小学生のころはずっとオール5。神童なんて呼ばれたこともあった。IQテストなんかやったら、今でもかなりい いレベルまでいくんじゃないかな。小学生のころから剣道も始めて高校2年生まで続けたし、硬派なところもあったんですよ。でもね、勉強やスポーツができる ことって、僕には大して大事なことではなかった。成績がいいことを先生や親に褒められても、別段気分いいとも思わなかったしね。むしろ、いつもどこか居心地の悪さを感じていました。
中学から受験校の武蔵高校に進んだんだけど、そこは田園調布に住んでいるような医者や役人の子どもばかりが通っている学校でした。1学年150人 くらしかいなかったけれど、商売人の子どもって僕ともう一人しかいない。そのもう一人も、銀座に映画館を何件か持っている家の子どもだった。とにかく中学 時代は、これまでに会ったことないような子ばかりに囲まれて過ごしたんですよ。こんなこともあったな。あるところのお坊ちゃんが家に遊びに来たときにラー メンの出前をとったんだけど、そのお坊ちゃん、「ラーメン食べるの生まれて初めて」って真顔で言うんですよ。お前ウソ言うんじゃないよってくらい、本気で 驚いちゃったね(笑)。
<小黒一三をつくったルーツ.2>
中学から夜遊びとバンド活動開始。大学では海と編集バイトに明け暮れる
僕の家には、築地の魚河岸で働いているお兄さんたちが一緒に住んでいて、大人の社会の“いろは”は、大概そのお兄さんたちから教えてもらった。それ で、中学2年のころにはすでに夜の遊びを覚えてしまったんです(笑)。夜な夜なディスコやクラブのようなところにも通ったし、バンドを始めたのもそのこ ろ。バンドっていっても、僕の場合はなぜかブルーグラスとロックのバンドだったんですね。ブルーグラスって何? っていう人もいるかもしれないけれど、ウ エスタンのルーツにあたるような古い音楽ですよ。中学生でブルーグラス・バンド組んでいるなんて、僕たちだけだったんじゃないかなぁ。
当時、青学にブルーマウンテンボーイズっていうバンドがあって、それが女子大生に人気だったんです。それなら僕らはブルーグラスだって始めたわけだけど、 中学生の女子には理解されずに挫折。後輩でロックバンドやっているグループがちやほやされていたから、じゃあ今度はロックだと思って僕らが選んだのはロー リング・ストーンズ。だけど当時の中学生が好んで聴いていたのは、ビートルズやグループサウンズのような音楽でしたからね。難しくて受けない。何するにし てもこんな感じで、どこまでもひねてんだよねぇ、僕は。
慶応義塾大学に進んでからは、海遊びばかりやっていました。逗葉ヨットクラブというところに入って、時間があれば神奈川の葉山でヨットを繰ってい た。そのころはディンギーと407といった競技艇が流行っていたんだけど、僕が好きだったのはクルーザー。でも、そうした海の遊びも3年ほどで卒業。大学 2年生のころから始めていた編集のバイトが忙しくなってきたんです。それは早稲田に通っていた兄貴の仲間たちが始めた編集プロダクションで、実にいろいろ な仕事をやらされました。女性週刊誌の怪しい香水占いの記事つくったり、相性診断の記事つくったり。そうやってバイトで稼いだお金は、またまたそのころは まりだした麻雀で、早稲田の先輩たちにどんどん巻き上げられていくっていう展開。本当に漫画みたいな毎日を過ごしていたんだなって、今さらながら思います。
<マガジンハウスへ>
業界最強の組合がある出版社に入社。編集採用にもかかわらず、営業部へ配属
僕が大学に行っていたころって、学生運動が盛んだったでしょう。学校は封鎖、ロックアウトで授業なんてほとんどなかった。でも当時から僕は、機動隊 にも活動家にも賛同できなかったなぁ。夜、新宿なんかで遊んでると、両者が激突する場面に出くわすことがしばしばあったけれど、正直、どちらもうざったい なぁって感じだった。今の環境雑誌に対するスタンスも、そのころと変わっていないと思います。ひとつのことを愚直に信じている人たちを見ると、何を根拠に そんなに熱くなっているんだって思っちゃう。僕には「挑戦し続ける」とか「何かを成し遂げるために」とかいった思いはまったくないんです。そもそもそんな ことできないし、関心がない。自分の人生なんだから、自分のままでいたいだけなんですよ。そのほうがよっぽど潔いと思うんだけどな。
大学を卒業して、マガジンハウスへ入社しました。昔から雑誌が好きでしたからね。中学1年生のときには、会報誌をつくってみんなに配っていた。先にも話し たように、武蔵中学というのは頭のいい子がいる学校なんだけど、僕から見ればみんな子どもっぽいわけ。そこで、性の知識をふんだんに盛り込んだ大人社会の いろいろなルールをしっかり教えてあげようと、自分で雑誌をつくったんです。それがけっこうな人気だったんだけど、ホームルームのときにある生徒が「先 生、小黒君がこんなことをやっています」って密告しやがった(笑)。そのときから僕は、密告者は絶対に許さないって誓ったんです。
そんなですから、僕は中学生のときからすでに前科者だった。当時のマガジンハウスは、日本の出版界で最強の組合があったこともあって、ここでもい きなりロックアウト。編集採用にもかかわらず、最初に配属されたのは営業部。ちょうどそのころ、会社にコンサルタントが入って「社会性のない部署(編集部 のこと)に最初から入れるから、いろいろな問題が起こるんだ」ってことになって、新入社員はまず最初に営業や総務のような業務に回されたんですね。でもろ くな仕事なんてない。周りの社員を見ると、みんな会社の外でお金を賭けて自転車操業している。すごい会社に入っちゃったなって思いましたね。でもそれが許 されていた時代でもあったんです。
<社員編集時代のスタート>
『ブルータス』時代に大暴れ。数々のとんでもない逸話を残す
小黒は業務では使いものにならないという理由で、『月刊平凡』の編集部に異動したのが2年後。その後、『ブルータス』『クロワッサン』『ガリバー』 と渡り歩くけれど、『ブルータス』が一番長くて、8年くらいかな。アフリカでゾウを撮影するのに1000万円の経費を落としたって話が流布してるようだけ ど、あれは景山民夫が吹聴しすぎて、かなり尾ひれがついちゃったみたいですね。本当は40~50万円の撮影代を普通に支払っただけですよ。リチャード・ア ベドンという有名なカメラマンがいたんですが、彼が『ヴォーグ』の撮影で使ったアフリカゾウがいて、それはアメリカで一度調教されたものだったんですね。 そのモデル・ゾウを使って撮影しただけの話です。
当時、海外の取材旅行といったら、せいぜい5日間から1週間くらい だったんだけど、僕はアフリカやアマゾンに行ったら、40日以上帰ってこなかった(笑)。そうした破天荒な取材を許してくれた当時の編集長、石川次郎さん は本当に偉い人だなぁって、いまだに感謝しているんです。でも帰国してから、そんな勝手なことやるんだったら、企業をきちんと説得してからやれって忠告を 受けた。僕の仕事に対する基礎、つまりスポンサー集め、資金調達のノウハウは、このころにできたんじゃないかと思う。僕のような人間に投資してくれる、奇 特な人のお金を気持ち良く使ってあげること、投資家が納得してくれるお金の使い方をすること、納得してくれる企画をつくることが、僕にとって夢のスタート なんです。
マガジンハウス時代で面白かった仕事といえば、横浜のバーの話かな。これは今でいうある種やらせのようなものなんだけど。スタジオの中に熱帯魚が 泳ぐ巨大な水槽を設置したバーをつくって、それを誌面で紹介したら、その記事を見た人たちが「あれはどこにあるんだ」って騒ぎ始めたんですね。そうこうし ているうちに、その記事そっくりのバーを誰かが本当につくっちゃった。嘘から出たまこと。まぁ、僕たちの仕事って、こういうことなんじゃないかと思う。な いものをいかに実現させていくかということですから。
スローフード、スローライフ、ロハス……、
それは「21世紀の国境なき新しい道徳」だね
<ケニアのマサイマラにホテルをオープン>
勢いでつくったケニアのホテル。評価は高いが経営は大赤字
『ブルータス』の取材でアフリカに行く前、僕はニューヨーク特集を担当していました。そこでキース・へリングやバスキアたちが描いた絵を見て、なん だかアフリカのアーティスト、サイモン・ジョージ・ムパタの絵に似てるなと思っていた。当時ニューヨークでは、ニュー・ペインティングって呼んでいました が、これって原点はアフリカなんじゃないかと。それから、西アフリカと東アフリカでアフリカ・モダンの絵描きたちを取材しているうちに、自分はムパタの絵 が好きなんだなぁってことがしだいにはっきりしてきた。それで、どうしてもムパタ本人に会いたいと思うようになったんだけど、実現するまでに2年くらいかか りましたね。いよいよムパタに会えるってときは、銀座の文房具屋でアクリル絵の具やキャンバスを購入して、勇んで持って行きましたよ。まぁ、相手にすれば 大きなお世話なんだけどさ(笑)。
絵を描いてもらっている間は暇だから、それほど動物好きでもないのに、サ バンナに繰り出して動物みたり空を眺めたり。それまで都会でずっとせっかちに過ごしてきたから、雲なんてゆっくり眺めることもなかったけれど、すごく気持 ちがいいんですよ、雲や風の流れる感じが。でもここには、こうした気持ち良さを体験できる施設がない。それで、これまたおせっかいなんだけど、ケニアのマ サイマラ国立保護区にホテルをつくりたくなってしまったと(笑)。そのホテルづくりは、マガジンハウスに在籍しながら始めたんだけど、当時の社長だった木 滑さんという人が粋な人でね。「会社を休職してやればいい」って言ってくれた。でも結局は組合がそれを許してくれなくて、自ら辞表を書いて退職する結果に なりました。200人くらいから300万円ずつ出資してもらって、僕は3000万円を出してホテルづくりに乗り出したはいいけれど、案の定、そんなにうま くいくわけはなくて、それはそれは大変でした(笑)。
当初の見積もりなんて、あってないようなもの。どんどん足が出て行くし、そのたびに追加出資が必要になる。1992年に「ムパタ・サファリ・クラ ブ」としてオープンにこぎつけましたが、開業後も赤字続き。従業員が130人いるっていうから、本当にそんなにいるのか確認するために、ポラロイドで全従 業員の顔を撮影しろって言ったら、現地人の支配人と副支配人が逃亡してしまいましてね(笑)。彼らが従業員数を水増しして、お金を横領していたんです。と まぁ、ほかにも政府に何度もだまされたりといろいろあって、経営が軌道に乗るまでにはずいぶん時間がかかりました。でもこのところは何だか盛況なようで予 約が取りにくくなっているらしい。最近は、ヨーロッパもアメリカも都会のほうが危険ですからね。テロリストもゾウやキリンを殺そうとはしないだろうから、 サバンナのほうがよっぽど安全かもしれません。
<月刊『ソトコト』創刊>
スローフード、愛知万博が追い風に!環境ビジネスの新市場を開拓
僕はマガジンハウス育ちだから、新しいライフスタイルマガジンというのをいつも考えていました。『ソトコト』を始めてからもう8年目になるけれど、 創刊当時は、新聞やさまざまなメディアで環境問題があれだけ論じられているにもかかわらず、それに対応できているライフスタイル・マガジンが一冊もなかっ た。それだったら僕がやろうと。ただ僕は、正義感から環境問題を語っていくことは避けたかったし、地味で質素なことが環境を考えることっていうイメージも 払拭したかった。環境問題を考えることは新しいオシャレであり、都会で生活している現代の人たちの新しいセンス、新しいライフスタイルとして、環境問題に かかわっていくための雑誌をつくりたいと思ったんです。
実際、環境問題はファッションよりもかっこ いい、知的な心のオシャレなんですよ。物質的なものがほぼ行き渡った現在、もはや物の価値を云々した差別化は難しいよね。あとは心の差別化しかないでしょ う。それがいまだに、勝ち負けだとか格差社会だとか、お金ではなくて心だとか、単純に二極化させた考え方、ものごとの捉え方がはびこっている。もっと自分 の感性に寄り添ったバランスをもっていれば、それでいいじゃない。それが本当の意味でいう、ロハス的な思考なんだと思う。
何事に対しても、僕は常に懐疑的ですからね。最近は、CO2の市場が立ち上がって、環境問題がCO2の高さに集約されることに危うさを感じていま す。今、この環境問題に問われている根源は、人としての生き方の問題なのではないかと。ちょっとかっこつけた言い方をすれば、「21世紀の国境なき新しい 道徳」、かな。創刊のころは、こうした『ソトコト』の考え方を理解してくれる大手広告代理店はほとんどなかったけれど、誰よりも早くこのオリジナルのスタ イルを打ち出して、自分たちで試行錯誤しながら続けてきたことが、今は自信になっている。もう誰も真似できないところまで来たって思いがありますからね。 この4月にはついに、『ソトコト』中国版が北京で発売になりました。
<未来へ~『ソトコト』が目指すもの>
ビジネスには興味なし。面白くて新しいことをしていたいだけ
これから僕が流行らせたいと思っているのは、ヨーロッパのラグジュアリー・ブランドを買いに行く時にエコ・バッグを使わせようというアイディア。ブ ランド好きの中にも、過剰包装は必要ないと思っている消費者は潜在的にたくさんいると思うんですよ。ブランド買いのために海外旅行する人たちとエコって一 見遠いようだけど、エコ・バッグを介してエコに貢献している賢いブランド好きっていう構図はできるよね。ブランド側からそれを提案するのは無理かもしれな いけれど、僕たちだったらそれは可能なんです。
こんなふうに、僕は自分でマーケットをつくるプロ デューサーだと思ってきたんだけれど、ある投資家から君はコンテンツ家だって指摘されて、ああそうかもしれないと思い至りました。確かにこれまで、ラジオ やBSの番組もやってきたし、いろいろなインターネット関連会社からコンテンツ提供の申し込みもあった。でも、いずれのクライアントも、組んでビジネスを やろうとは言うけれど、資金を提供してくれようとは言ってくれない(笑)。それじゃあいやだからと、ほとんど断ってきましたからね。もっと面白いマーケッ トを一緒になってつくろうというなら、こちらもいろいろな技術を提供してあげたいとは思っているんだけどなぁ。
そもそも僕は、ビジネスに興味ないんだよね。つくりたい雑誌がつくれて、僕が面白いと思った価値観を、一緒に広げていこうと思ってくれる仲間が増 えればそれでいいって思っているだけだから。そうした運用のためにはもちろん資金が必要だけど、それもイベントをやりたいとか本を出したいとかってことで やっている。どうにもお金を儲ける才には長けていないようなんだ。僕は狼少年みたいに、人をだましたり驚かしたりするのが仕事みたいなものですからね。今 も昔も人の営みは変わらないっていうけれど、人間関係にしても、男女関係にしても、ずっと同じなんてつまらないじゃない。朝起きたら、新しい一日が始ま るって感じを常に持っていたいんです。
<これから起業を目指す人たちへのメッセージ>
結局、ビジネスで成功を目指すなら、成功者の真似をするのが一番の近道
これはある人に教えてもらったことなんだけど、ビジネスで成功したかったら、成功した先人の真似をするのが一番の近道なんじゃないかと思う。僕みた いに頑なに独自性を貫こうとしている人間からの反省でもあるんだけどね(笑)。以前、ダイエー創業者の中内功さんから「君はなぜアフリカにこんなホテルつ くったのかね」って聞かれて、「こんなバカなことは誰もやらないと思いましたので」と答えたときにはっと気づいた。昔から落語が好きだったから、「バカだ ねぇ」って言われると嬉しいんだよね、僕は。そんなだから、分かれ道を目の前にすると、誰もこんなことはしないだろうってことを敢えて選んでしまう。子ど ものころから変わらずひねてるんだけど、50年以上生きてきて、これはさすがに無駄かなぁと思えてきた(笑)。だからこれから起業で成功を目指す人には、 まず成功者の真似をしなさいと言いたいね。 僕みたいによっぽどの変わり者じゃないと、世の中にない ものをつくろうなんて疲れるだけだし、実際つくれたものだって、そんな大したことないんだから(笑)。男の人でも女の人でも、たとえば「好きな異性はどん な人?」といった問いかけを自分にしたとき、その答えが「きれいな人が好き」「やさしい人が好き」といったものだったら、普通に成功ビジネスの真似をした ほうがいい。もしもその答えが「オカチメンコな人」とか「へそ曲がりな人」というのであれば、人がやらないことに挑戦してみてもいいんじゃないの。僕なん かは当然後者だから、それしかやりようがないんだけれどね(笑)。
<了>
取材・文:菊池徳行(アメイジングニッポン)
撮影:刑部友康